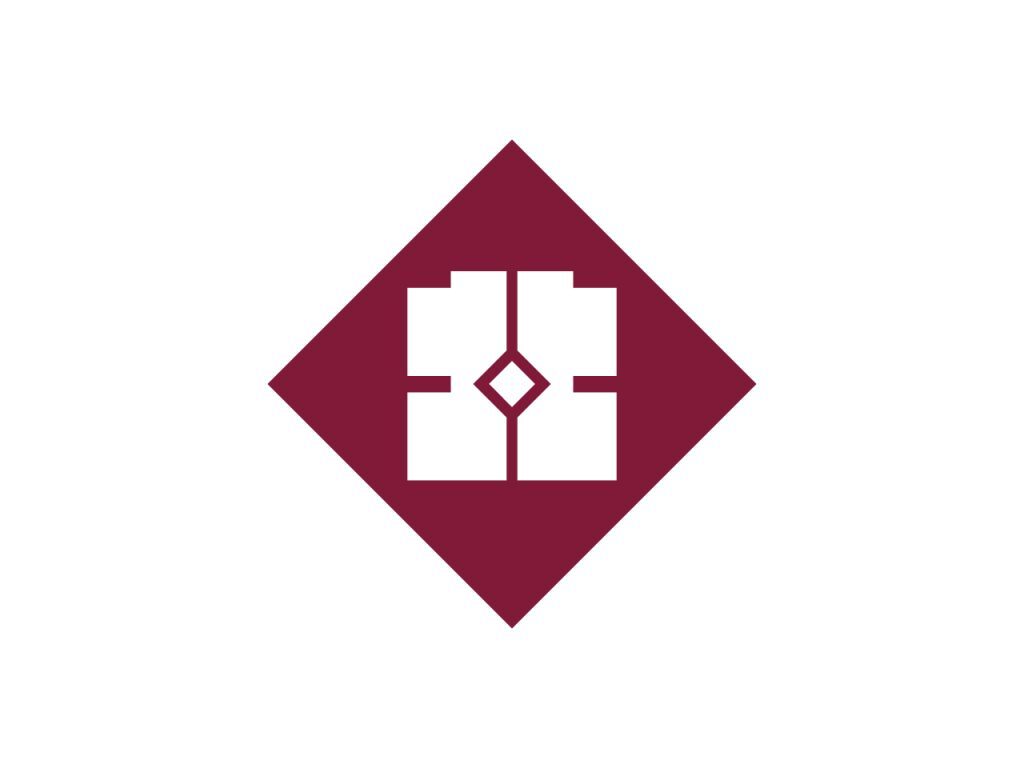COLUMN
住宅コラム
住宅の基礎知識
2025.10.04.Sat
家を建てるベストタイミングはいつ? 年齢・ライフイベント・資金計画から考える時期の見極め方

「家を建てる時期」は、それぞれの状況によって適切なタイミングが異なるため、全ての人に共通する「正解」があるわけではありません。しかし、結婚や出産といったライフイベント、30~40代という年代、あるいはある程度頭金の目途がついたときなど、多くの方が家づくりを具体的に考え始めるきっかけとなる時期には、いくつかの共通点が見られます。
本記事では、そうした「いつ家を建てるか」という多くの方が悩むテーマについて、ライフイベント、年齢、お金の準備といった視点から、自分にとって適切なタイミングを見極めるための判断材料を分かりやすく解説します。
「家を建てる時期」みんなどうしてる? 適切なタイミングの見つけ方
結婚や子どもの進学、退職後など、家を建てるのに適した時期は、個人や家族、それぞれ状況により異なります。しかし、多くの人が家づくりを検討するライフイベントや、ローンを組むのに適した時期は存在するため、これらを判断材料とするのもおすすめの方法です。
本記事では以下の4つのポイントから、家を建てるのに適した時期を紹介します。
- ライフイベント
- 年齢
- お金
- 社会情勢や季節
判断基準1:ライフイベントから考える家の必要性

結婚や出産、子どもの成長や独立などのライフイベントは、家づくりを考える大きなきっかけです。節目となるライフイベント別に住宅の必要性を紹介します。
結婚・出産:家族構成の変化
住宅金融支援機構の調査では、20代・30代が住宅購入を考えたきっかけとして、「結婚、出産を機に」「子どもや家族のため」といった理由が特に多くなっています(※)。
結婚をすればパートナーと新しく生活を築いていく必要があります。また、子どもが生まれれば、のびのびと遊べるスペースや、子ども部屋が欲しいと思う人は多いでしょう。家族構成が変化したときは賃貸物件よりも持ち家の方がより理想の生活を実現しやすいかもしれません。
北辰工務店では、子どもの成長に合わせて柔軟に対応できる間取りをご提案しています。
※参考:住宅金融支援機構.「住宅ローン利用者の実態調査【住宅ローン利用予定者調査(2023年4月調査)】」P5.3. 住宅取得の動機(年齢別)”.
https://www.jhf.go.jp/files/400366410.pdf ,(参照2025-05-06).
子どもの進学:学区や教育環境
子どもの小学校進学のタイミングは家を建てるのにおすすめの時期の一つです。理由としては、子どもが公立の小中学校に通う場合、学校は「学区」により自動的に振り分けられるためです。
学区は住んでいる地域により自動的に決まります。小学校入学後に別の地域に家を建ててしまうと、転校が必要になり子どもに負担もかかってしまうため、進学と同時期の転居は理想的なタイミングといえるでしょう。
なお、埼玉エリアでは浦和区や大宮区、千葉エリアでは市川市・市原市・成田市などが人気学区です。
キャリアや将来設計
ある程度将来設計の見通しがついたときも、家を購入するのに適しています。例えば、転勤の多い職種であればある程度キャリアが固まったときや、退職後に家を購入するケースもあります。
リモートワークが多いのであれば「働きやすい家」を検討しても良いでしょう。また、子どもが巣立った後なら、老後の過ごしやすさを重視しやすくなります。
北辰工務店では、家族の変化に柔軟に対応できる間取りや、お子さまや高齢者に優しいバリアフリー対応の住宅をご提案しています。
判断基準2:家を建てるなら何歳? 年齢と住宅ローンの関係性

家を建てるときの年齢で特に注意が必要なのが、住宅ローンの存在です。家を建てる年代別のメリットや注意点を紹介します。
若いうちに建てるメリット・デメリット
20~30代前半の若いうちであれば、住宅ローンの返済期間を35年のように長く取れるため、月々の返済負担を抑えやすくなります。また、繰り上げ返済を使えば総返済額が抑えられる可能性もあります。住宅支出の見通しもつき、資産形成がしやすい点もメリットです。
一方、貯金が少なく頭金を用意できなければ住宅ローン審査に通らない、返済額負担が大きいなどの問題が生じる恐れもあります。離職や子どもの人数の増加など、ライフプランの変動リスクにも注意が必要です。
30~40代で建てるメリット・デメリット
30~40代は仕事や収入が安定し、20代から貯蓄をしていれば自己資金にも余裕が生まれます。また、家族構成が固定されやすく、理想の間取りをイメージしやすい年代でもあります。金銭的余裕があり、将来を見据えた家選びがしやすい点がメリットです。
一方、住宅購入が後ろ倒しになると、定年後もローンの返済が必要になる恐れがあります。また、完済年齢が高齢であれば、ローン審査が通りにくいことがある点がデメリットです。
なお、住宅金融支援機構の調査によると、2023年度のフラット35の利用者平均年齢は44.3歳です(※)。
※参考:住宅金融支援機構.「2023年度 フラット35利用者調査」P4.Ⅰ 調査結果の概要”.
https://www.jhf.go.jp/files/400370694.pdf ,(参照2025-05-06).
年齢が住宅ローン審査や返済計画に与える影響
住宅ローンの多くは申し込み時の年齢が70歳未満(※)の方を対象としています。ただし、住宅ローンの審査では最終返済時の年齢(完済時年齢)を80歳程度としていることが多いです。あまり高齢になってから家を建てようとすると、ローンが組めない可能性があるため注意が必要です。
また、年齢が上がるほど組めるローンの制限が増えます。さらに、病気や親の介護など若いときとは別のリスクも生じやすいため、年齢リスクを考慮した無理のない返済計画を立てることが大切です。
※参考:住宅金融支援機構.「【フラット35】ご利用条件」.https://www.flat35.com/loan/flat35/conditions.html ,(参照2025-05-06)
判断基準3:お金の準備はOK? 貯蓄・年収・住宅ローン金利
頭金は十分か、金利動向はどのようになっているかなど、家を建てる時期を「お金」の面から解説します。
自己資金はどれくらい必要?
国土交通省の報告書によると、注文住宅の住宅建築資金と自己資本、自己資本比率は以下の通りです(※)(土地購入資金は除く)。
| 地域 | 住宅建築資金 | 自己資金 | 自己資本比率 |
| 全国平均 | 3,459万円 | 972万円 | 28.1% |
| 大都市圏平均 | 3,843万円 | 1,332万円 | 34.7% |
家を建てるときは、土地・建物の費用以外に、不動産会社に支払う仲介手数料や各種諸費用、購入時の手付金などが必要です。自己資金の目安は地域により異なりますが、900万円~1,300万円程度を用意するケースが多く見られます。
なお、住宅ローンのみで家を建てることも可能ですが、諸経費の支払いには自己資金が必要となるため、ある程度のまとまった現金を準備しておく必要があります。
※参考:国土交通省 住宅局.「令和3年度住 宅 市 場 動 向 調 査 報 告 書」P98.“3.4 資金調達に関する事項”
無理のない資金計画と年収の目安
家を建てるときは、返済負担率(返済比率)の確認も大切です。返済負担率とは、世帯収入に占める住宅ローン返済額の割合のことで、一般的には20~25%以下が理想とされます。
なお、住宅ローンの借入額の目安は世帯年収の5~7倍程度とされています。例えば、世帯年収が600万円であれば2,500万~4,200万円程度が目安です。
北辰工務店では、展示場や相談会で住宅ローンの専門スタッフが相談や借入れのシミュレーションを行っています。
住宅ローン金利や税制優遇の動向
家を建てるときは、住宅ローンの金利や住宅取得に関連した税制優遇制度も確認しましょう。
例えば、代表的な住宅ローン金利には金利が変わらない「固定金利」と、半年ごとに金利が変わる「変動金利」があります。また、税制優遇措置では「住宅ローン減税」があります。これは、年末のローン残高の0.7%を所得税などから最大13年間控除できる制度です(※)。
これらの制度が充実しているタイミングであれば、住宅取得に必要な総支払額を抑えられたり、税制上のメリットを受けられたりする可能性があります。ただし、これらの制度はあくまでも補助的な要素として捉え、多角的に購入時期を検討することが大切です。各制度の内容は変更される可能性があるため、確認するようにしましょう。
※参考:国土交通省.「住宅ローン減税」.https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html ,(参照2025-05-06).
判断基準4:社会情勢や季節も考慮に入れる?
建築費や地価の動向は総費用に影響します。また、建築資材の中には天候や気温の影響を受けるものもあるため、建築時期の季節を考慮することも大切です。タイミングを考える上で参考になる社会情勢や季節の考え方を紹介します。
土地価格や建築費の動向
家を建てるときにかかる費用は、大きく「資材価格」「人件費」「土地価格」に分けられます。これらの費用は社会情勢によって変動しやすいため、家を建てる時期によって総費用が大きく変わることがあります。ただし、長期的な費用の高騰や底値を正確に予測することは困難なため、現状を確認しつつ、希望の時期を決定するのが良いでしょう。
なお、埼玉・千葉エリアの公示地価では、前年比2~4%程度の上昇が見られました(2025年5月時点)(※)。円安の進行や、建築業界の人材の高齢化、運送業の労働改革などにより高騰が続いています。
※参考:埼玉県.「令和7年 地価公示結果の概要」p1.https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/265989/01_r7gaiyou.pdf ,(参照2025-05-07).
※参考:千葉県.「令和7年地価公示に基づく地価動向について《千葉県》」p2.https://www.pref.chiba.lg.jp/youchi/toukeidata/chika/documents/01r7k-gaiyou.pdf ,(参照2025-05-07).
建築に適した季節や引っ越しのタイミング
一般的に、住宅の建築は気候が安定し、降雨量の少ない春や秋が適しているといわれています。一方、猛暑となる真夏や厳寒期の真冬、長雨が続く梅雨の時期は、作業効率や建材への影響を考慮すると、避けられる傾向にあります。
理由としては、木材や基礎コンクリートなどが雨の影響を受けやすいためです。このため、お子さんの進学など、希望する入居時期が決まっている場合は、そこから逆算して住宅の建築計画を立てるのがおすすめです。
北辰工務店では契約から住宅のお引き渡しまで、9~11カ月程度お時間をいただいています。また、季節に応じた対策も行っているため、詳細はご相談ください。
自分たちにとっての「建て時」を見極めるために
これまで挙げたさまざまな判断基準から、各自の状況に当てはめて総合的に判断する方法を紹介します。
優先順位を付ける
家を建てるときは、さまざまな面から計画を立てる必要があります。しかし、検討事項が多く、何を重視すれば良いか分からなくなってしまうこともあるでしょう。そのようなときは、優先順位を付けるのがおすすめです。例えば、以下のチェックリストを参考に、自分たちにとって重要な要素は何かを確認してみましょう。
【チェックリスト】
- いつまでに家を建てたい?
- どこに家を建てたい?
- どんな間取りにしたい?
- 土地建物の予算はいくらにする?
- いつまでに返済したい?
これらを洗い出し、特に譲れないポイントを見つけましょう。
専門家への相談も有効
家づくりを進める中ではさまざまな疑問が生まれますが、中には自分たちだけでは判断が難しいこともあるでしょう。そのような場合は、まず専門家に相談し、客観的なアドバイスや具体的なサポートを受けてみるのも有効な手段です。
北辰工務店では、土地探しや予算計画、土地を生かした家づくりのプランニングなど、家づくり相談を実施しています。これらの相談会を活用することで、家づくりに関する不安や疑問を解消し、理想の住まいのイメージをより明確にすることができるでしょう。家づくりで少しでも分からないことや不安なことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
【まとめ】 焦らず、適切なタイミングで理想の家づくりを
家を建てるのに適切な時期は、それぞれの家族の状況やライフプランによって異なります。納得のいく住まいづくりを実現するためにも、将来設計、予算、希望の地域や間取り、入居希望時期、社会情勢など、さまざまな角度から総合的に検討することが大切です。焦らず、一つひとつ着実に計画を進め、ぜひ理想の家づくりを実現してください。
もし、家づくりで迷うことがあれば、北辰工務店にお気軽にご相談ください。電話・メール・イベントにて、相談対応を実施しています。
OTHER COLUMN